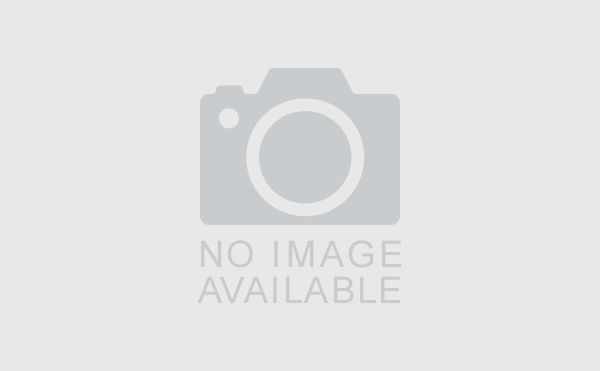【東大・大海研】共同研究集会_第11回水族館シンポジウム 「水生生物研究機関としての水族館。その将来像を探る。」(2025年12月15日・16日開催)
| 主催 | コンビーナー: 猿渡敏郎 (東京大学大気海洋研究所) 植田育男 (神奈川大学) 栗田正徳 (名古屋港水族館) 杉野 隆 (東京都井の頭自然文化園) |
|---|---|
| 日程 | 2025年12月15日(月)13:00~18:00 2025年12月16日(火)09:00~16:30 |
| 場所 | 東京大学大気海洋研究所講堂 (ポスター掲示:エントランスホール) |
| 概要 |
水族館は、水生生物を専門に扱う社会教育研究機関である。日本国内には、海なし県を含め全国に70以上の水族館が存在し、老若男女が水生生物を楽しみながら学べる場となっている。日本の水族館の飼育技術は、世界で初めてマグロ類の長期飼育技術を確立し、ナンキョクオキアミやサンマの継代飼育に成功するなど、世界トップレベルにあり、水生生物の学術研究にも大いに貢献している。水族館とアカデミアを有機的につなげる場を提供しようと、平成17年より隔年で、当時の東京大学海洋研究所、そして現在は大気海洋研究所の全国共同利用研究集会として、通称水族館シンポジウムを開催してきた。毎回、研究、環境問題、教育など、テーマを変えて開催し、令和5年には第10回水族館シンポジウムを開催した。水族館関係者に限らず、水生生物を扱う大学、博物館、研究機関の研究者、そして水族館愛好家の間でも広く認知されたシンポジウムとなっている。過去の講演を基に、二冊の単行本、『水族館の仕事』、『研究する水族館』を出版した。 第11回となる本申請のシンポジウムでは、当初のシンポジウム開催趣旨に立ち返り、水族館における研究をテーマとする。生体展示を行うには、水生生物の採集、運搬、蓄養、順化、展示という一連の作業を要し、どの段階においても経験に根差した確固たる技術を要する。飼育・展示を通して、同一個体の継続観察、繁殖行動など、野生化では観察すら難しい水生生物の生態に関する知見を得ることができる。このような水族館ならではの研究成果の紹介と、研究機関と連携した学際的な共同研究の紹介を通して、水族館の水生生物教育研究機関としての将来像を構築することを目的とする。 詳細は下記Webサイトをご覧ください。 詳細はこちら |
| 問い合わせ先 | 猿渡敏郎(東京大学大気海洋研究所) Email:tsaruwat(at)aori.u-tokyo.ac.jp (at)を@に変えて送信してください。 |